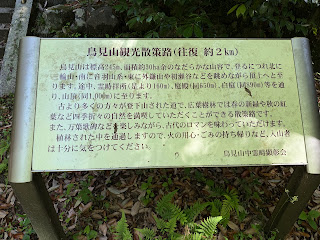次に目指す忍坂山口坐神社(おしさかやまぐちにますじんじゃ:奈良県桜井市赤尾42)は等彌神社のさらに東、直線距離にして1.6kmじゃけど、それこそ鳥見山霊畤がある鳥見山が間に挟まっとるのでぐるっと廻る必要があり、道過距離にして2.4kmある。
そっち方面に行くバスもあるようなので、運がよかったら途中から乗ってしまうかと思いつつ一旦北に向かって国道165号線に出て、東に歩き始めた。
国道に出るとすぐに薬師町という奈良交通のバス停があったので時刻表を見てみると何と、休日は1日にたった3本、9時28分・11時59分・16時38分発のみ…。
まあ基本は学生さん用なんだろうなあ。
これでバスの可能性はゼロと判明したため歩くしかない。
しかし本当につまらん道だなあ。
あまりのつまらなさに写真を撮る気も失せていたため、Googleのストビューを貼り付けてみたが見ての通りの無機質な道。
街道名は「伊勢本街道」という風雅なものなんじゃけど、実際歩いてみれば何の特徴もない単なる地方3桁国道であり、面白そうなものもないし面白そうなことが起きそうな雰囲気もない。
この道を30分以上も歩くのは本当につまらんかった。
こんなつまらん道を時間かけて歩くのはしんどいので可能な限り早足で歩き、忍坂山口坐神社入口とも言うべき「忍坂」交差点に通常より早く達した。
神社はここからもう目と鼻の先じゃ。
境内へは粟原川の逆っ側(西側)から入ることになる。
境内手前には恐らく参拝者用と思われる駐車スペースがあり、3~4台は停められそうじゃ。
因みに今回クルマを使わなかった理由の1つに「駐車スペースの有無が心配」というのがあったんじゃけど、結果的には3ヵ所とも駐車できる環境じゃった。
駐車スペースと境内の境目辺りには竹が2本立っていて、細い注連縄が張られとる。
それをくぐって境内に入ると右手に案内板が立っとる。
 |
| © ill-health(ruephas) 2025 |
内容はこうじゃ。
忍坂山口坐神社忍坂街道・キーワード金閣寺延喜式内社・山口神社は全部で十四社で、うち十三社まで県内にあります。そのうち飛島・石寸・長谷・畝傍・耳成・忍坂の山口神社が最も大切に祀られてきました。ここの二代目楠の木は巨樹として有名ですが、初代楠の木は室町時代に京都の金閣寺を建立する時、天井板として利用されたと言い伝えられ、その時倒れた先が隣村の忍坂まで届いたので、今も「木の下」という地名が残っています。大和の古道紀行一般社団法人 桜井市観光協会
ははあ。
まさかの金閣寺の天井板か。
もったいないことするなあ。
いや、この金閣寺天井板話も勿論大事じゃけど、やはり御祭神のこととか由緒歴史にも触れてほしいなあ。
そういやあこの辺の神社には、静岡とかでよくあるような神社説明板がないなあと改めて思う。
 |
| 浜松市にある熊野三神社の案内板 市か県の教育委員会あたりが作ってる気がする こういうやつがどんな神社にもあると助かるんだけどなあ © ill-health(ruephas) 2025 |
ここも石寸山口神社と同様、規模的には決して大きくはない(いや、まあむしろ狭い部類じゃろう)が、木立に囲まれているのにお陽さまの光が境内によく届き爽やかな雰囲気なのがとても良い。
木立の間を風が通り抜けて行くし、気分が落ち着く。
 |
| ほら、なかなか爽やかでしょ 夏に良さそう © ill-health(ruephas) 2025 |
ワシは社殿(拝殿)の方に歩いていって早速参拝した。
 |
| 質素だけど荒れた様子なし 氏子さんたちのおかげじゃろう © ill-health(ruephas) 2025 |
見ての通り、拝殿と本殿兼用の簡素な社殿(中見たけど本殿内に普通にある鏡とか太鼓とか何もないので、もしかしたら拝殿のみの本殿なし?)で、ワシのタイプ分けでは「ブリキロボット顔面タイプ」に属する(わかるでしょ)。
各種情報を見ると、さっき行った石寸山口神社にしてもここ忍坂山口坐神社にしても、長い歴史と重要な役割を持つ神社だと思うんじゃけど、社殿や境内の風景や表情はそんな感じは全く見せていなくて、ほんとに村の中にある質素で小さなお社であって偉ぶったところが全然ないのがいいぞ。
四国の荒ぶり系大山くんとも、静岡県東部の山の神・酒の神系大山くんともすこし違ったタイプ大山くんだなあと思った。
書き加えておくと、忍坂山口坐神社の御祭神は当然大山祇命で創建年代は不詳。
旧社格は村社。
人によっては寂しいと感じるかもしれんが、ワシにとってはいい空間の神社じゃった。
さて参拝も済んだし、そろそろ戻ろう。
あの無味乾燥な国道165号線を桜井まで歩いて戻すのは真っ平御免なのでワシは一計を案じ、神社から北方向にある朝倉台という住宅地に向かって歩き出した。
それを抜けるとすぐに近鉄大阪線 大和朝倉駅があり電車が頻発しとる。
下りは勿論桜井に行くし、その先大阪上本町まで区間準急や急行が5~10分ヘッドで出とる。
本日はこれに乗り、桜井を通り越して大和八木まで出向き、駅前にある焼肉屋でビール片手に焼肉をつつくことにしよう。
それからアパートに帰っても、14時開始の中日阪神戦のテレビ中継開始には十分間に合うじゃろう。
 |
| 大和八木駅から徒歩数分にある回転焼肉屋で昼飯 カルビの定食とホルモンなど美味しく頂いた 勿論ビールと麦焼酎のロックも美味しく頂いて完食 © ill-health(ruephas) 2025 |